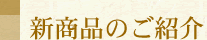 |
| 太子間道の御召 |
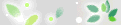 |
|
|
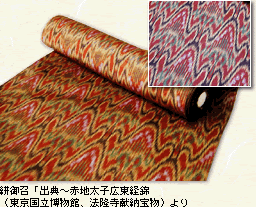 |
 |
文様の出典は法隆寺献納宝物の裂地で太子間道の名で古来著名である。
聖徳太子が勝鬘経(しょうまんぎょう:インド勝鬘夫人に対し釈迦が教えを説いた仏教教典)を講賛された際、幡(ばん仏・菩薩や法要の場を荘厳供養する旗)にこれを用いられたとの伝承からその名がある。
間道の名ではあるがこれは縞ではなく、絣の技法(経絣)による日本に現存する最古の裂で、五色の絹糸で織られている。 |
|
 |
インドから中国の絹産地、広東に伝わった絣の技法によるもので、広東錦として日本に渡来した(飛鳥時代)と考えられている。同様の裂が正倉院御物にもあるが、絣はそのあと室町時代の末頃まで見られない。近世に至って南蛮貿易によってもたらされた縞に伴って、絣もみられる様になるが、日本での本格的な絣の発達は江戸中期以降のことである。
この文様がなにを意味するかは以下諸説あるが、正倉院の奈良中期の染織文様に較べて古様である。
1)山岳を象形化したもの、東南アジア地域のイカットに広く分布している人像文様
(両手足を広げて立つ姿)ともみえる南方的文様である。
2)天地創造、万物の根元を「気」とする中国の古代思想を反映し、
沸き立ちのぼる「気」を表現した吉祥文様である。 |
|
|
|